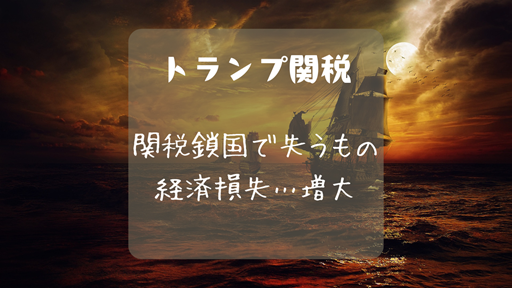トランプ関税で日本車メーカー激震!
~日産USA・スバルが語らないアメリカ雇用の裏側~
ここ数日、アメリカ市場における日系の自動車業界から次々と発表される”シフトチェンジ”のニュースに、静かに耳を傾けています。
コスト削減、雇用の安定――たしかに言葉だけを見れば、希望がにじむ未来図なのだけど。最近の調査では、こうした動き主にはトランプ関税などへの不支持が60%を超えたという声も届き始めました。本当にこの道は、私たちアメリカ在住者にとって、政界経済にとっても、良い未来へとつながっているのでしょうか。
にゅうわ的なまなざしで、少し立ち止まりながら、今起きている変化を見つめてみたいと思います。
🌊
スバルは人気車撤退へ、その影に潜む崩壊
–アメリカ市場の日系自動車業界の方向転換から見えるもの–
静かに流れるニュースの裏側で、「雪崩のように迫る危機」が、じわじわと押し寄せています。アメリカ市場における日系自動車メーカーのシフトチェンジです。そこには「コスト削減」や「効率化」といった、前向きな言葉が並びます。けれど実際には、これまでの”稼ぎ頭”だった収益源が細り始め、未来へ向かうための”小さな痛み”が、確実な現実になりつつあるのです。
たとえば、スバルです。
カナダ向けの輸出が大きく減少し、人気のアウトバックも、2026年以降はカナダ市場から姿を消す予定です。いまは「工場を止めず、調整で乗り切る」としていますが、それは強まる向かい風のなかで、かろうじてバランスを取ろうとしているだけではないのでしょうか。本当は、静かに足元から崩れ始めているのかもしれません。
労働組合(Union)の力もあり、すぐに大規模なリストラには踏み切れない現状なのです。表向きは「安定」を装いながら、水面下では売上減少と雇用不安という、避けられない現実がじわじわと広がっています。損失は、すでに確定しているのです。ただそれを「一気に崩さないように」、静かに、時間をかけて処理しているだけに見えるのです。
まるで、春先に溶け始めた雪の下で、見えないところで川が増水していくように…。私たちの目に見えないところで、確実に「地形」は変わりつつあります。
“アメリカファースト”を掲げたはずなのに…現状、アメリカで働く人たちにとっては、雇用が減り、製造ラインが止まり始めるこの現実に、どれだけの人が気づいているのでしょうか?この経済損失によりアメリカには、不景気の波──いや、確実に、スタグフレーションの影が押し寄せています。
一方で“生産シャッフル”ならぬ、その流れとは真逆の恩恵を受けているのが、実は日本なんですね。カナダ市場向けの生産がアメリカから撤退すれば、その分の製造は日本へとシフトするのだそう。これはつまり、日本国内の工場にとっては“チャンス”でもあるということです。もちろん、それが即「雇用増」や「景気回復」につながるわけではないですが、長期的に見れば、グローバルサプライチェーンの再構築が、日本に一部プラスに働く可能性はあるあります。
アメリカが“関税鎖国モード”で壁を作るほどに、自国経済はジワジワとダメージを受け、逆に、冷静に再構築を進める国のほうが、静かにチャンスを手にしていくことになるでしょう。
アメリカ在住者としては、「自国第一!」が、結局自滅第一になっていく様を間近で見ていくのは辛いですが、日本人としての目線では、「やっぱり品質と信頼性は、日本製なんだな」とちょっと誇らしくもなるのです。アメリカにいると、その矛盾と現実が、日常の風景に滲んで見えてきます。
🌊
日産USAの工場閉鎖が示す“EV戦略の迷走”
–日産が突きつけた静かな現実:EVセダン計画中止–その先にあるものは?
お次は日産です。
日産が発表した「EVセダン計画の中止」とミシシッピ州カントン工場での新型EV生産の延期は、単なる戦略変更ではありません。それは、静かに、しかし確実に「現場」にしわ寄せをもたらす現実の始まりです。当初予定されていたLZ1F(日産ブランド)とLZ1E(インフィニティブランド)は、日産のアメリカにおける次世代EVの柱となるはずでした。しかし、セダン市場の縮小、EV価格競争の激化、そして想定を下回る販売予測を受けて、このプロジェクトは撤回されました。
日産は表向きには「競争環境への対応」「投資の最適化」と説明していますが、実態は極めて厳しいのでしょう。効率化という名のもとに削られるのは、数字では測れない、働く人々の生活と地域の未来です。「EVシフト」はもはや自動車業界の既定路線──そう信じられてきました。しかし現実には、充電インフラの未整備や、価格への不信感、そして政策支援の不安定さが、消費者の足を止めています。日産もその波に飲まれた形です。
アメリカの労働者にとって、これはただの「方針転換」ではありません。製造ラインの見直しは、すなわち雇用の縮小であり、生活の不安そのものです。「アメリカファースト」を唱える声が大きくなる中で、実際にアメリカ国内の雇用が減り始めている──ここでも声を大にして言いたいです、「アメリカ国民よ、この皮肉な現実に、気づいているのでしょうか。」
これは一企業の選択ではなく、アメリカという国の「産業の地盤」が揺らぎ始めている兆しなのかもしれません。アメリカの自動車産業が直面する根深い問題、そして、時代の波に翻弄される労働者たちの現実を浮き彫りにしています。効率か、生活か、企業が取る「合理的な選択」の裏で、静かに、しかし確実に削られていく未来となります。その現実から、私たちは目を背けてはいけないはずです。
🌊
アメリカ市場の変動とサプライチェーン再編
–静かに進む「新・鎖国時代」–
日系メーカーが試練に立たされ、アメリカ市場からの押し出しが進んでいる一方で、他国の企業もまた、静かに、しかし確実に動き始めています。
ステランティスは900人の一時解雇を発表しました。ホンダ、GM、ボルボも、相次いでサプライチェーンの再編に踏み切りました。その背景には、変動を繰り返す関税政策がもたらす価格設定の難しさが、静かに影を落としています。
表向きには「経営戦略」として語られるこれらの動きですが、その実態は、まるで「新たな鎖国時代」かのようにも錯覚します。かつて広がり続けたグローバル化の流れが、いま、静かに後退し始めています。各企業の調整は、単なる効率化だけでは終わりません。予測不可能な経済の荒波に翻弄される中で、「どう生き延びるか」というサバイバルの選択が、サプライチェーンに深い爪痕を刻み始めているのです。一度アメリカ市場から離れたグローバルなサプライチェーンはそう簡単には戻ってくることはないでしょう。
この静かな激動の中で、アメリカ経済はじわじわと孤立を深め、企業たちは「自分たちだけで守れるもの」と「他者と繋がり続ける意味」とを、問い直される局面を迎えています。
🌊
米国製車両に迫る25%の壁
–カナダの報復関税、その静かな衝撃–
カナダが米国製車両に最大25%の報復関税を課す決定を下しました。表面上は一つの貿易摩擦にすぎないように見えるかもしれません。しかし、その波紋は想像以上に大きく、静かに競争力の根幹を揺るがしています。
アメリカ市場で輝いてきた米国製車両たちは、カナダ市場では突然、重たい足枷をはめられることに!出口戦略の一角だったカナダ向け輸出は、急速に厳しい局面へと追い込まれ始めています。報復関税という「見えない壁」は、これまでのスムーズな流れを遮断し、米国企業にとって新たな戦略、そしてリスク管理の再構築を迫るものとなるでしょう。
目の前に広がるのは、先の読めない「地雷原」だったのです。
ひとたび足を踏み外せば、想定以上の損失を招く──そんな不安定な地形が、今まさに形を取り始めています。
🌊
トランプ関税が生む長期的な逆風
このトランプ関税政策は、一見すると米国内の産業を守るための手段として魅力的に映ります。しかし、その裏側には、長期的な雇用減少や市場縮小というリスクが静かに潜んでいるのが現実です。
短期的には確かに国内産業を守る効果を見せていますが、経済の大局を見れば、その影響は予想以上に深刻なものへと進展しかねない状況にあります。
実際に、企業はリスク分散のため、米国一国への依存から静かに離れ始めています。日本、メキシコなど、より柔軟な供給拠点へとシフトする動きが加速しており、かつての「強固な米国内生産体制」は、知らぬ間に足元から侵食されつつあるのです。
思い返せば、かつてGMをはじめとする米企業が、産業の空洞化によって一つの都市、一つの地域を衰退させた痛い歴史がありました。その教訓は、アメリカ経済にとって忘れてはならないはずでした。
ところが今、トランプ氏の掲げる政策は、まるで何十年も前のマニュアルを再び開いたかのように、時代遅れの手法に固執しているように見えます。グローバル化が進んだ現代においては、もはや有効性を失った戦略かもしれないにもかかわらず。世界の動きは、米国市場に過度に依存していた時代はすでに終わり、静かに、新たなサプライチェーンが築かれつつあるのです。この流れが意味するのは、米国内の生産拠点の空洞化、そして、失われることを待つだけの雇用です。
今はまだ「アメリカファースト」の看板が掲げられています。ですが、その土台の亀裂は、すでに静かに、しかし確実に広がり始めているのです。
🌊
「アメリカファースト」が「アメリカラスト」へ。
かつて「アメリカファースト」と叫ばれた旗印が、今、静かに「アメリカラスト」への道を歩み始めているのかもしれません。国内産業を守るために掲げられた貿易政策は、短期的には守りの姿勢を見せていますが、実際にはじわじわと、そして確実に、国内の雇用と産業の足元を侵食し始めています。
世界はすでに国境を超えて深く結びついており、孤立を選ぶことがどれだけ大きな代償を伴うのか、その現実はこれからますます浮き彫りになっていくでしょう。
「安定しているように見える雇用」は、実のところ、静かに崩れ始めています。
今こそ目先の利益や一時的な勝利に酔うのではなく、長期的な視点で、未来に向けたしなやかで現実的な戦略を描くべき時ではないでしょうか。
これ以上、「取り返しのつかない代償」を払わないために──。
こちらでは真面目に語ってるけど、こっち:Noteでは少し肩の力を抜いて、ニヤッと笑える行間を楽しんでます。ニュースの隙間に転がる“皮肉とリアル”、拾いに来てみませんか?
→【アメリカ】日産×スバル、北米戦線縮小:経済損失と雇用不安がいよいよ現実に-トランプ関税-